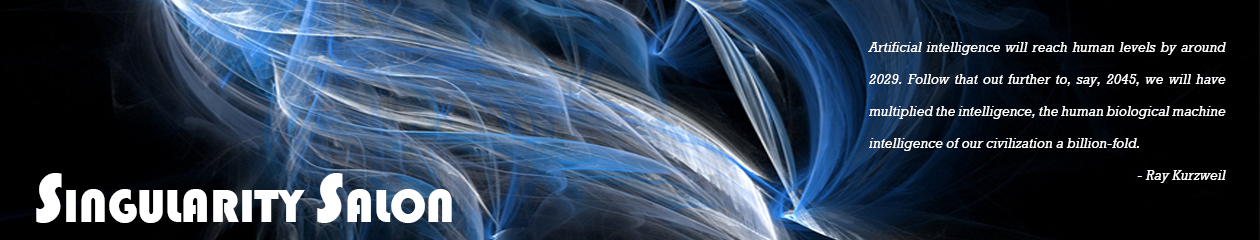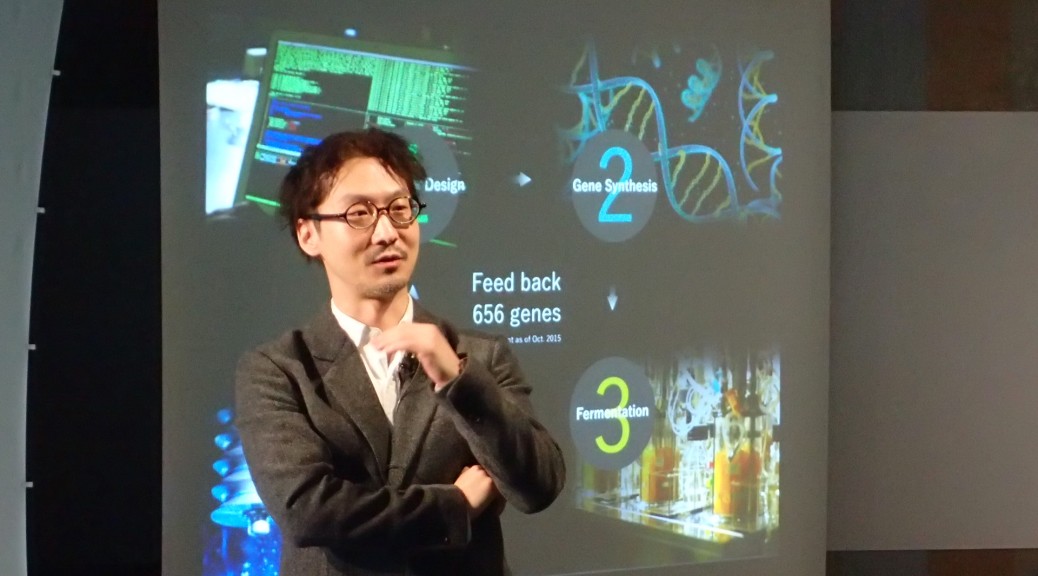さる2016年1月31日(日)、グランフロント大阪・ナレッジサロンにてシンギュラリティ・サロン「第12回公開講演会」を開催しました。
今回は、理化学研究所 生命システム研究センターチームリーダーで全脳アーキティクチャ・イニシアティブの理事・副代表を務める、高橋 恒一氏が、「人類を再発明するのに必要なこと」と題してお話されました。
以下、講演要旨です。
—————–
シンギュラリティー=人類の再発明
自己改良するAIによる爆発的な科学技術の発展、つまりシンギュラリティーが2045年ごろに起こると言われている。そうなれば人類の歴史上最も大きな出来事になるであろう。そのようなことは本当に起きるのだろうか、そしてそれは本当に2045年頃に起きるだろうか?今日はこのことについて真剣に考えてみたい。
シンギュラリティーに向けて、ロードマップを幾つかの段階に分けて考える必要がある。非常に大雑把に言えば、まずは一般に入手可能な計算機の能力がヒト並み(1H)に到達する2030年頃までの15年、次に人類全体を凌駕する2045年頃までの15年間の二段階がある。
現在から2030年までで具体的な壁となっているのは、プロセッサのエネルギー効率(発熱)だ。熱密度はすでに限界に到達しており、さらなるコンピュータの性能向上のネックになっている。半導体の微細化に関するムーアの法則が終わると言われている2020年ごろ以降も能力向上を続けるためには、ノイマン型から脳(ニューラル)型への移行が必要だろう。脳型コンピュータへの移行が実現できれば、あと3桁から6桁の性能向上は可能なので、2030年ごろに1Hの計算機を一般に普及させることも可能だろう。
しかし、2030年頃以降の性能向上継続は現状ではまだ具体的な方策が見えておらず、もう少し慎重に考えざるをえない。おそらく、生命科学の知見が重要になるだろう。生物のエネルギー効率はとても高い。スーパーコンピュータ「京」は、ほぼヒトの脳に匹敵する演算能力をもっていると言われるが、京の消費電力は10MW。一方、ヒトの脳は10〜20W。ヒトの一個体全体の消費エネルギーは概ね100W程度だが、すべての体細胞で行われているDNA検索を現行のコンピュータにやらせると、原発50億基分の電力が必要だ。まさに桁違いの差がある。生命の情報処理メカニズムをとりいれた脳型コンピュータができれば、熱密度・エネルギー消費効率の問題は解決できるかもしれない。生命科学がヒントになるのは人工知能だけではない。山形県の鶴岡市にスパイバーという会社も生命の超効率性に注目して、遺伝子情報に基づいたバイオ素材で石油化学工業に依存する世界を救おうとしている。
ちなみに、なぜ生物はこんなに高い効率で情報処理を行えるのだろうか?最近、私たちは、DNAの微視的なゆらぎが細胞内のゲノム情報処理を可能にしていることを発見した。分子は溶液中の熱ゆらぎを積極的に利用し「ぶるぶるふるえる」ことで、超低エネルギーで遺伝情報へアクセスできていることがわかってきた。
汎用人工知能開発競争は日本にも勝機あり
汎用人工知能を取り巻く状況は、昨年あたりから大きく変わってきた。Google/DeepMind社が国際学会で汎用人工知能開発を公表したのをはじめ、海外ではGoodAI、Numenta、Vicarious、OpenCogなど、日本では全脳アーキテクチャ、記号創発ロボティクスなどの、さまざまな企業や活動がでてきている。
私が副代表を務めるNPO法人・全脳アーキテクチャイニシアティブ(WBAI)も、昨年ハッカソンを実施するなど活動を開始した。全脳アーキテクチャのアプローチは、脳型の認知アーキテクチャを、機械学習を統合して実現すること。そのためには、認知科学、計算機科学、神経科学を融合することが重要になる。
そして、共同作業の基盤となるのが、我々が開発しているBriCAだ。BriCAは、神経科学と認知アーキテクチャを記述言語で組み立てるための基盤ソフトウェアである。BriCAを発展させて、サービスロボットやビッグデータ解析、科学研究などの様々な応用に共通に利用できる脳型認知アーキテクチャのミドルウェアを作りたいと思っている。
汎用人工知能開発は世界的な熾烈な競争だが、日本にも勝機はある。ノイマン型から脳型への移行という大きな変革時期である今は、日本にとってチャンスだろう。脳(ニューラル)型コンピュータや機械学習は作り込み型技術だが、これは元来日本人が得意とする分野だからだ。
また人工知能の経済的な価値は、実社会にいかに浸透できるかにかかっているが、AIを使いこなすスキルにつながる「ヒューマン・エージェント・インタラクション」分野でも日本は進んでいる。
第5の科学=AI駆動型科学によるパラダイムシフト
サイエンスは、第一の科学である経験記述から、第二の科学である理論、さらにコンピュータの発展により可能になった第三の科学であるシミュレーション、そして近年盛り上がりを見せる第四の科学であるデータ駆動型科学へと進んできた。これらを統合したサイエンスを、AIをつかって「まわす」ことができるようになれば、サイエンスは加速度的に発展するだろう。
AIをサイエンスに応用しようという試みは今までにいろいろ行われている。例えば、火星探査機バイキング向けに計画された「デンドラル」(自律的な土壌サンプル分析)、スタンフォード大学AIラボの「マイシン」(投薬提案システム)、ロス・キングの「ロボットサイエンティスト」(分子遺伝学の実験と仮説推論の自動化)などがある。コーネル大学のAIラボでは、力学的カオス系であり複雑な振る舞いをする2重振り子の動きをカメラを通してAIに観察させ、振り子軌道の抽出から支配法則(不変量)の発見までを、AI(Genetic Programming)に行わせることに成功している。これらに最近の機械学習で可能になった特徴量の自律的な抽出を組み合わせれば、さらに発展できるだろう。
今後5年から10年で有望と思う分野には、データの認識・分類・測定が重要な分野、論理推論、確率モデルが重要な分野、人間の認知能力の限界をおぎなう分野などがある。重要なことは、実験もふくめてAIにやらせることだ。そうでないと「発見のサイクル」を自動化、高速化できないからだ。
私も参加しているスタートアップ企業、ロボティック・バイオロジー・インスティテュート(RBI)株式会社は、生命科学の実験自動化するロボットを製品化した。プロトコルを共有して同時並行で実験を行なう。将来的には、ロボットセンターに1万台〜10万台のロボットをおき、共有プロトコルをそれぞれのロボットがダウンロードして同時並行で実験を行う構想だ。現在、味の素、慶應大学、医科歯科大、九州大、産総研と理研で共同実験をおこなっているが、将来は全世界でやりたい。実はこのアプローチは、私の友人が作ったクックパッドという料理レシピのサイトがヒントだ。実際、彼らのプロトコル共有のノウハウをいれながら進めている。
人類の再発明に必要なこと
冒頭でも述べたように、2030年頃のヒト並みのAIの実現には期待が持てる。シンギュラリティー実現には、2030年頃から2045年頃までの技術発展をいかに継続させるかが非常に大きな課題である。
そのための鍵が、「第5の科学=AI駆動型科学」である。20世紀までの科学は、天才が一人いればできたが、今は複雑すぎて不可能になった。人工知能によるパラダイムシフトが必要で、その鍵となるのがAI駆動型科学だ。
「第5の科学=AI駆動型科学」の実現と発展が日本にとっても人類にとっても重要な理由が三つある。
第一に、科学技術イノベーションの自動化は第四次産業革命の起爆剤の本命である。そもそもシンギュラリティー到達前に日本が先進国から脱落したら元も子もない。
第二に、今日は計算機ハードとAIソフトウエアの二点についてお話ししたが、生命科学やナノテクノロジーなども含めた科学技術水準を総合的に高めて行かないとシンギュラリティー到達前の2030年代あたりに技術発展が息切れが起きる公算が高い。
そして第三に、人類の科学技術が十分発展する前に知的活動の主体が人工知能に移ってしまうと技術的特異点を人類に制御不可能な形のハードテイクオフで通過する可能性が高まる。この点が実は一番大事かもしれない。AIが自律的に進化して「勝手に」シンギュラリティーに到達する、という議論が多いが、その際、人類が理解できるようなプラットフォームを作っておかないと、AIが何をやっているのか人類にはまったくわからなくなるおそれがある。Future of Life Instituteのヤン=タリンが心配しているのもこの点だ。ハードテイクオフではなく、ソフトテイクオフに持っていく必要がある。
すなわち、「人類を再発明するために必要なこと」とは、第5の科学=AI駆動型科学である、というのが今日の結論だ。
—————–
*今回は配布資料はありません。
(報告:保田充彦)